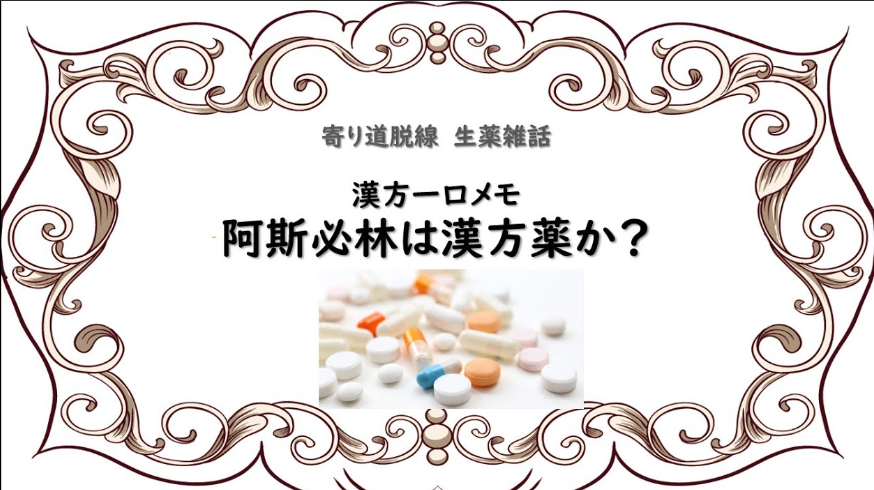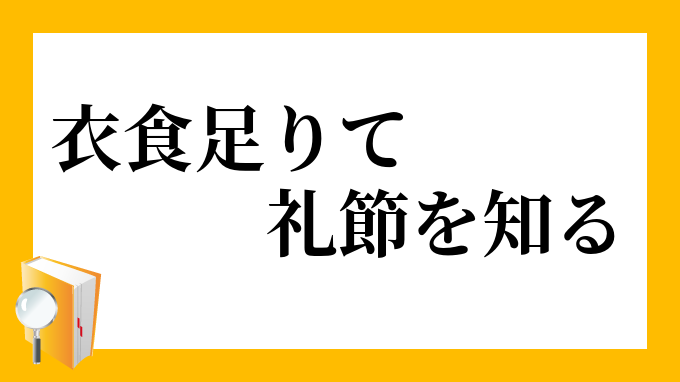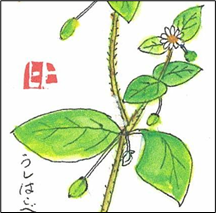【100話】新年明けましておめでとうございます

お正月の挨拶として「新年明けましておめでとうございます」がありますが、この挨拶の仕方は少し変で、間違っているのです。 「明けまして」には二つの意味があって、一つは「新しい」、もう一つは「終わって」との意味を持っています。 「新しい」の意味で見て身ますと、「新年」新しい年が新しくなって、と新しい重なってしまいます。 「終わって」にはこんな例があります。梅雨明け(梅雨が終わって)、盆明け(盆が終わって)、喪が明ける(喪が終わって)、夜明け(夜が終わって)などを見ますと、「新年明けまして」は「新年が終わって」となり、お目出度いとはいかないですね。 従って、正しくは「新年おめでとうございます」か「明けましておめでとうございます」になるのではないでしょうか。