【044話】ショウガ祭り
「ウワッセ、ワッセ。」
町内を練り回った祭神輿が最後の大きなうねりを見せ、担ぎ手の掛声とともに鐘や太鼓のお囃子が秋の残照の中にかき消されようとする頃、祭りのクライマックが訪れようとしていました。
JR東京駅から、中央線・青梅線・武蔵五日市線を乗り継いで1時間半、奥多摩に向かう車窓からふと目にとまった東秋留(ヒガシアキル)駅の、ここは秋川市二宮神社の境内です。
9月9日は二宮神社の例大祭で、地元の人々は「秋留ショウガ祭り」と呼んでいます。昼ごろから並び始めた露店がギッシリと軒を並べる頃には、名物のショウガ売りの声が聞こえきました。ショウガを扱う店は30軒ばかり。20本ほどを一束にして、そこには赤地に白文字で書いた「参拝記念厄除二宮生姜祭」の護符が掛かっています。
千葉、埼玉、群馬、神奈川などの近郊から持ち込まれたショウガは、一晩で4トン以上が買われていきます。3束4束と買い求める人、親せきにも配るのだと小脇に抱えて帰る人。むせかえるショウガのにおいの中で一年の無事息災を願う人々の顔が生き生きしています。
二宮神社の創建は定かではありませんが、承平天慶の乱(931-947年)の折、俵藤太(藤原)秀郷がこの神社に戦勝の祈願をしていますので、少なくとも千年以上前からあったことになります。藤太は平将門を討ち果たし、社殿、玉垣を造営したと伝えられていて、さらに建久年間(1191年)には、源頼朝が久社領千石を寄進したとの伝承もあります。
二宮神社の祭りがショウガ祭りと呼ばれるようになったのは江戸時代になってからで、健康を守る食材としてショウガを崇めたのが始まりです。
ショウガはインドから東南アジアが原産地です。「魏志倭人伝」に「薑」という字があることから、ショウガは三世紀にはすでに日本に伝来していたことになります。
ショウガは別名ハジカミとも呼ばれていますが、元来ハジカミとは山椒のことで、古名としてクレノハジカミとあるのは呉(中国)から渡ってきた山椒に似た味のものとの意味のようです。
現在、日本には多くの栽培品種があって、小ショウガ系と大ショウガ系に大別されます。関東地方では、芽ショウガ(葉ショウガ)として食用にする谷中(ヤナカ)、金時といった小型品種が主に栽培されていますが、一方、高知、熊本、長崎では土佐一、ジャンボ、カンボ、インド、長崎一号のような大型品種の栽培が盛んです。
中国料理においては、ショウガは欠かすことのできない材料の一つです。川魚や川エビなどの河川の幸をふんだんに取り入れた中国料理にあって、その臭みを取る目的とともに、心身を温める作用を期待しています。
大和のショウガの奈良漬はおつな味だし、伊勢のショウガ板も郷愁を与えてくれます。日本にはショウガを使った多くの食べ物がありますが、最近ではショウガジャムやショウガ餅、ショウガの砂糖漬けも多く目にするようになりました。身体に爽やかさを呼び戻してくれるショウガ酒やジンジャーエルもあって、確実にしょうがの需要は増してきています。
古くから用いられてきたショウガですので、言い伝えられた多くの民間療法があります。
○生のショウガの絞り汁に熱湯を注いで飲むと船酔い、車酔いに効く。
○生のショウガの絞り汁に熱湯を注ぎ、これで温罨法すると、しもやけによい。
○しゃっくりには生のショウガ汁をいっきに飲む。
○筍、茸、獣肉、魚類などの中毒には、生のショウガの汁を飲む。
○咳には生のショウガを擂り潰した絞り汁に、砂糖または蜂蜜を加え、熱湯を注いで飲む。
○胃がつかえて食の進まない時は生のショウガを食べる。
○嘔吐の気味があれば、カラスビシャク(半夏)と一緒に煎じて飲む。
○生の絞り汁を熱く煎じて、肩や背中の凝っているに塗り、その上に和紙を当て、更に布で覆っておくと翌日には凝りがとれる。
漢方薬の生姜、乾姜はともにショウガの根茎を使用するものです。漢方では、生姜は生のショウガを、乾姜は干したショウガを用いるのですが、日本においては干したショウガを干生姜と呼び、生姜の代用としてもよいとされ、乾姜は蒸して乾かしたショウガを用いることが多いようです。
芳香成分のモノテルペン類やセスキテルペン類は生のショウガと乾燥したショウガではその含量に大きな差があり、これらの芳香成分は薬理活性成分の一つと考えられていることから、日本漢方での生姜、乾姜の使い方には問題が残るところです。
また、辛味成分のジンゲロール類とショウガオール類については、ただ干しただけのショウガと蒸して乾かしたショウガでは、その構成比が異なっていて、それぞれの辛味成分は異なった薬理活性が報告されていることから今後十分な検討が必要です。
以上の修治からの問題点の他に、ショウガの根茎部位や採集時期、大ショウガや小ショウガの栽培品種においても成分的な違いがわかってきました。
陽が沈み、露店を照らす裸電球に輝きが増すころ、ショウガ祭のハイライトが始まります。町内を練り歩いてきた神輿が二宮神社の境内へ続く急な石段を担ぎあげられます。しかし、ショウガをかじり、お神酒が入った担ぎ手の若者たちにはこの険しい階段を上る力は残っていません。
御輿に縄をかけ、上から引っ張り、下から押し上げ、群衆が一つになって、祭りはフィナーレを迎えます。そして、満ち足りた顔が家路につくのです。この夜はどこの家でもショウガを食べます。ショウガに味噌をつけて食べます。
秋留のショウガ祭の余韻が残っている間に、芝増上寺の鎮守、芝の神明さまで知られる芝大神宮で9月11日から10日間のダラダラ祭りが開かれます。境内にはショウガを売る市がたつのでショウガ祭の名があります。このショウガははメッカチ生姜、目腐れ生姜と呼ばれています。
9月22二日。大宰府の秋祭り。ショウガを買って帰り、味噌漬けにしておくと火事の火元にならないとの俗説があります。
また、東日本では八朔にショウガを贈る風習があるのも除災の呪いに由来するものでしょう。



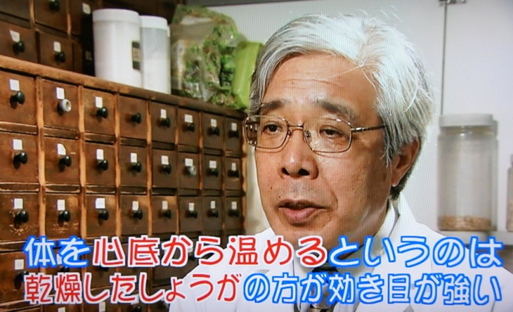

コメント
コメントを投稿